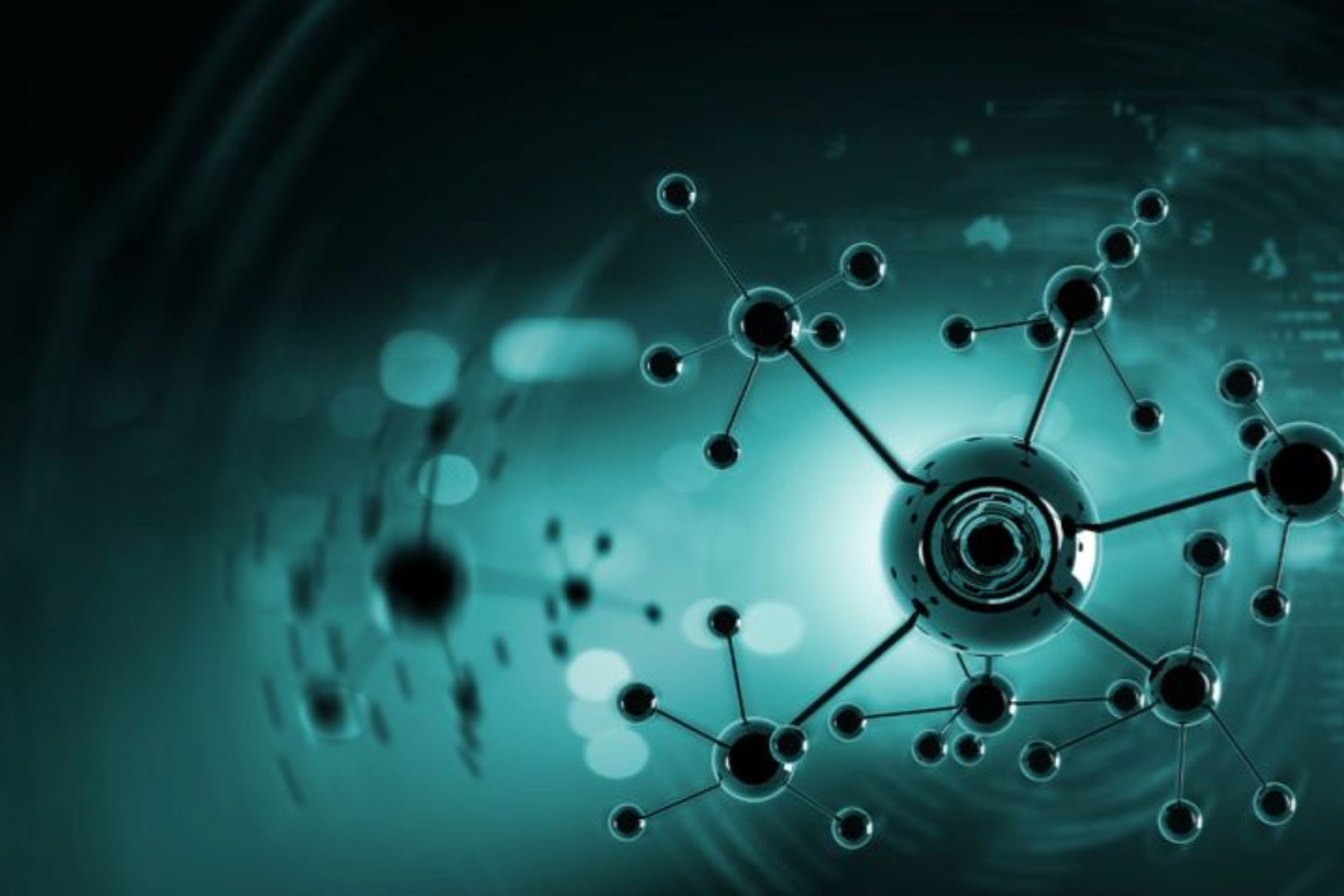原作者:Twitter@Mingz_
原編集者:王漢宇
出典:Twitter @N_SpaceDAO
現在のNFT市場は、BAYC、CryptoPunks、Azuki、その他のWeb3.0ブランドなど、並外れた価値を持つ多くの優良プロジェクトですでに活発になっており、NFT PFPはIPと同様の豊富なリソースを利用して、商業的に大きな影響力を発揮しています。前提として、投資家間の再販取引のみがプロジェクト当事者に豊富なNFTロイヤルティをもたらすことができ、これはこれらのプロジェクト当事者が多額のお金を稼ぐのに十分です。 NFT PFPのためのこれらのブランドプロジェクトパーティーの壮大な青写真と野心において、ある種の絶妙でおなじみの「ペイントケーキ」スキルの存在を指摘する必要があると言うなら、同時に次のことも認めなければなりません。これらのブランドの活力の源は、将来の軌道と市場領域の継続的な拡大によって保証されます。
しかし、NFT PFP の将来のトラックの影響力と市場価値は大きな影響を受けており、ゲーム、アニメーション、高度にインタラクティブなメタバースなどのさまざまな新しいオーディオビジュアルメディアによって形成される「ハイパーメディア」環境は、ユーザーの没入感を変革し、また再構築されています。彼らの新しい世界観は、必然的にNFT PFP市場にある程度の脅威をもたらします。ブランドプロジェクト側が依然としてPFP市場の一つの調査に執着していると、執拗な精神から頑固化、保守化する危険があり、市場の多様化に伴いその商業的限界が今後もクローズアップされ、ひいては問題を引き起こす可能性もある。過去に活躍していたブランドの色調が失われることは、自身のブランド価値の低下につながります。
副題
日本製作委員会とは?
1990年代初頭以来、日本の映画・アニメーション市場では、主に投資リスクの分散を目的とした映画、アニメーションおよび関連付帯商品の投資シナジーを指す「製作委員会」と呼ばれる製作投資モデルが徐々に広く採用されるようになった。生産流通プロセス。当時の商業映画やアニメーション作品は、前工程の撮影・制作と後工程の宣伝・配給の両方に長期間と膨大な人材が必要でした。多くの高品質 IP の開発と制作を断念する代わりに巨額の投資を行う余裕がないことがよくありましたが、市場開拓における製作委員会モデルの成熟により、アニメーション フロントエンド制作の資金と人材の不足という最大の問題点が解消されました。 。
日本のアニメ制作費の高騰にはそれなりの理由がある。 1962年当時、手塚治虫の原作『鉄腕アトム』の制作費は1話あたり210万円、つまり約12万元だった。 1982年、美少女アイドルとロボット戦争というテーマを組み合わせた画期的な作品「マクロス」の製作費は1話550万円、約33万元だった。日本映画史上の画期的なアニメーションである「エヴァンゲリオン」の1エピソードの制作費は、1995年までに600万円、つまり約36万元にまで上昇した。
組織構造に関して言えば、製作委員会は本質的に商業協力組織の一種であり、特定のアニメーションプロジェクトに基づいて複数の企業によって設立され、日々の投資、企画管理、利益分配を担当します。通常、製作委員会のメンバーは配給会社、制作会社、テレビ局、広告媒体社、出版社、アニメ制作スタジオ、オーディオビジュアルメーカーなどで構成され、その中でも配給会社や制作会社が中心となることが多い。製作委員会の幹事会社(下記の通り)。

周知のとおり、アニメ産業自体が高投資・高リターン・高リスクという市場特性を持っており、アニメーション制作において単線投資モデルを採用すると、制作会社やアニメスタジオのみが負担することになります。制作前コストと制作後コストのすべて。つまり、単線投資モデルによるアニメーション制作は作品の質に大きく左右され、作品の制作レベルと演出の質が投資の成否と利益を直接決定することになる。戻り値。製作委員会の登場は、資金難により公開できなかった多くのオリジナルアニメや非人気オリジナル作品に幅広い市場注目の機会を提供し、徐々に台頭していく作品を強力に促進したと言える。京都アニメーションなどの中小アニメーション制作会社が市場に出ています。
Web3.0の分野に話を戻すと、現在の市場状況は大手優良企業(さらにYuga LabsがCryptoPunksを買収)と疎外された中小ブランドによってある程度独占されていることがわかりましたが、内部構造は全く同じです。たとえば、BAYC などの IP は、その多面的な影響力、十分なトラフィック レベル、および暗号ネイティブの追加により、業界で揺るぎない独占的地位を獲得していますが、そのようなブランド プロジェクトの場合、リソースは同じではありません。なぜなら、資本主義と新自由主義のもつれが交渉や陰謀によって築かれたビジネス帝国と同じように、その優れた資源こそが、業界における「一流」のブランドイメージを慎重に維持することを可能にしているからである。しかし、多くの中小ブランドIPプロジェクト当事者にとって、リソースは最も需要が高く、競争も激しいものであり、Web3.0の分野でも独自の蓄積を活かして常に都市を攻撃している。利点。
アニメーション分野における中小制作会社が直面する極めて困難な問題が、Web3.0市場環境において再解釈されつつあることがわかる。優れた想像力と並外れた創造性を備えたブランドプロジェクトチームの多くは、ひとえに人材不足によるものである. および資金源がコンテンツ制作と価値実現において困難に直面しています。一方で、市場の調整メカニズム自体は、ブランドプロジェクト関係者にとってはある意味諸刃の剣でもあり、暗号化分野やNFTトラックは標準化・厳格化・体系的な開発傾向にある一方で、市場の調整メカニズムは両刃の剣でもあります。フィードバック効果も当初の狂信から冷静な合理性へと落ち着きつつあり、このような自主規制により、ブランドプロジェクト当事者は創造性と生産性のバランスの問題を解決する必要があります。企画制作業界のレベル向上と市場評価メカニズムの最適化により、素早いポンプ・アンド・ダンプ(出荷の引き上げ)を追求する行為は容易には実現できなくなりました。ただし、Web3.0 の固有の匿名性と創造性の市場志向が、まず想像力豊かな新しいチームに比較的平等な競争の場を提供する場合、これらの新しいチームの挑戦的な創造的なアイデアは、破壊的イノベーションの力へのフィードバックとなることにも注意する必要があります。市場の。
日本製作委員会には、DVD販売会社、玩具会社、制作会社、広告代理店、出版社、テレビ局など、さまざまなところから出資者が集まっています。そして、Web3.0 によって構築される新しい製作委員会は、このモデルを踏襲したいと考え、プロジェクト当事者の市場運営計画に応じて自由に組み合わせを変更することができます。主要なNFTブランドプロジェクトで一般的に採用されている将来計画ロードマップに関する限り、その投資源はコンテンツ制作、専門的なリスク管理エンド、クロスメディア制作サービス、オフライン配信など、さまざまな方向で検討できることがわかります。 Web3.0がプロデュースする新たな制作委員会は、NFT PFPプロデューサー、潜在的なベンチャーキャピタル機関、ゲーム制作会社、周辺制作会社、オフラインパブリッシャーなどの組織で構成されます。
日本製作委員会には、DVD販売会社、玩具会社、制作会社、広告代理店、出版社、テレビ局など、さまざまなところから出資者が集まっています。そして、Web3.0 によって構築される新しい製作委員会は、このモデルを踏襲したいと考え、プロジェクト当事者の市場運営計画に応じて自由に組み合わせを変更することができます。主要なNFTブランドプロジェクトで一般的に採用されている将来計画ロードマップに関する限り、その投資源はコンテンツ制作、専門的なリスク管理エンド、クロスメディア制作サービス、オフライン配信など、さまざまな方向で検討できることがわかります。 Web3.0がプロデュースする新たな制作委員会は、NFT PFPプロデューサー、潜在的なベンチャーキャピタル機関、ゲーム制作会社、周辺制作会社、オフラインパブリッシャーなどの組織で構成されます。
日本制作委員会の投資モデルを継承しつつ、Web3.0の制作体制における大きな違いも指摘する必要がある。国境を越えた資本主義のグローバル化とWeb3.0、NFTの概念の出現という二重の状況下で、コミュニケーション形態のレベルに着目すると、日本製作委員会はアニメーションというメディア商品を中心に構築された投資協力組織であることが判明した。 PFP の出現は、新しいコミュニケーション価値システムとパターンを生み出しました。たとえば、Web3.0 ブランド プロジェクト関係者は通常、IP 著作権を所有しており、コンテンツを制作する際にコミックの原作者と同じ創造的自由を持つことができます。 , 様々なバックグラウンドを持つ投資家と対峙する際に十分な株式差別化と交渉優位性を有しており、これは日本のアニメ制作会社が製作委員会において直面する制作状況とは根本的に異なる。近い将来、Web3.0 が IP 著作権を持つブランド プロジェクト関係者に豊富なトラック オプションを提供し、彼らがこの状況を利用して、自社のブランド価値属性に適合する開発パスを見つけることになることを予測するのは難しくありません。 。
日本製作委員会は、アニメーションを流通手段として中心に設立された組織です。しかし、世界的に見ると、商業的に成功しているメディアは必ずしもアニメーションだけではなく、NFT PFPの登場によって新たなコミュニケーション価値体系も提供されています。また、日本のアニメ制作会社とは異なり、Web3.0ブランドプロジェクト当事者は漫画の原作者と同様にIPの著作権を保有しているため、交渉やエクイティの差別化においてある程度のメリットがある。将来的には Web3.0 の発展に伴い、ブランド プロジェクト関係者は、自身のブランド開発パスに合わせてより多くの選択肢を得ることができます。
注: 日本のアニメーション制作会社は通常、アニメーション IP の所有権を所有していません。現在のWeb3.0環境では、ブランドプロジェクト当事者はまずNFT PFPを使用して独自のIPを宣伝し、トラフィックと市場効果を蓄積します。そのため、ブランドプロジェクト当事者はIP所有者とNFT PFPトラックプロジェクトのプロデューサーの両方になることができます。投資家との二重アイデンティティ矛盾していません。
副題
投資の多様化
「軽く数千万円に達するアニメ制作費を考えると、これらの企業が単独で制作に投資することを許されると、一度の失敗が致命的な打撃を与える可能性があります。長い目で見ると、作品の品質が保たれるかどうかは重要です」番組が縮小されたり、オリジナル番組が放棄されたりした場合、視聴者の減少を引き起こし、業界全体の収益性が低下し、業界の発展が終わりのない悪循環に陥ることになります。」
アニメやゲーム制作などの業界は、多額の資金援助が必要なため、プロフェッショナリズムの欠如と運営プロセスにおける資金の枯渇という二重の問題に直面する可能性が高く、最終的に完成した製品の品質が低くなる可能性があります。それはまた、中小規模のプロジェクト当事者にとっては研究開発を断念せざるを得ないジレンマにもつながった。同様に、Web3.0におけるブランドIPプロジェクト当事者が初期投資や第一弾のNFT PFP発行利益のみに依存して研究開発を推進すると、必然的に同様の生産ジレンマに直面することになる。新しいシリーズの PFP が開発されたり、新しいトラックが普及したりする予定です。投資リスクを最大限に回避するために、多くのブランドプロジェクト関係者は、多大なプレッシャーの下で品質管理の取り組みを削減したり、生産基準を積極的に引き下げたり、あるいは単にイノベーションの可能性を放棄したりすることを選択する可能性があり、それは好開発サイクルに取り返しのつかないダメージを与えることになります。業界の。
副題
ウィンドウ操作
「運営窓口により、アニメ制作会社が単独で商業運営を行う重責はなくなり、製作委員会がその後の業務を一元的に管理します。製作委員会は、それに応じて最適な専門組織を見つけて商業運営を遂行します」テレビ局への番組放送・配信の引き継ぎ、広告代理店への広告企画・販売の引き継ぎ、玩具会社への商品開発・ライセンスの引き継ぎなど、ニーズに応じた対応を行っていきます。」
言うまでもなく、中小のアニメ制作会社は商業運営の成熟度が十分とは言えず、商業運営よりもクリエイティブ制作に強みを持っていることが多い。このため、製作委員会の窓口運営により、配給などの特定業務は専門の「認定窓口」に委託され、各投資機関が作品制作の一連の流れの中で業務を遂行し、各事業セグメントを担当することとなります。アニメ制作会社の商業運用負担を大幅に軽減します。
副題
生産部門
制作会社の専門分業である「制作部門」は手塚時代に確立され、現在も続いている。製作委員会は資金を集めて制作の方向性を決定した後、当初の依頼と呼ばれる比較的有力なアニメ会社に後続の作業を委託した。同社は当初、アニメーションプロジェクトの制作プロセス全体の管理を担当するために招聘されたが、制作業務のすべてを引き受けるのではなく、実情に応じて一部のプロセスを他の中小企業に委託して完成させる予定だった。を「ダウンロード」といいます。 「ダウンロード」企業は、業務の一部を中小企業に下請けすることもあり、これは「二次ダウンソーシング」と呼ばれ、上位と下位の明確な階層構造を形成します。 」
生産分離モデルの主な理由は日本の市場環境にあり、日本にはディズニーのような規模で完全な工業生産資源を有するグループは存在せず、あらゆる種類の中小企業は継続的な強化を通じてのみ相互に協力することができる。相互協力とビジネス交流を促進し、産業の工業生産レベルを促進します。これは、日本が米国ハリウッドと競合するオーディオビジュアル製品市場を確立し、世界のオーディオビジュアル製品市場シェアの60%以上を獲得している理由でもあります。つまり、中小企業が大半を占める日本のアニメ会社は、この「棲み分け」された業界流通メカニズムと階層的生産システムを通じて、競争と協力が共存する一連の企業ネットワークを編み上げていたのである。この企業ネットワークでは、制作会社がすべて東京に集中しており、ビジネス協力や交流が促進される一方で、産業クラスターの規模が大幅に拡大し、日本のアニメーションおよびアニメーションの強力な制作能力が蓄積されます。ディズニーなどの大手。
ある意味、日本のアニメーション制作分野における中小企業の一般的な代表例は、Web3.0 の分散化と分散型産業構造の固有の特性に似ています。大規模な多国籍企業や寡頭政治の不在が実際に市場の「真空」を生み出しており、それが生産部門の出現と成熟によって業界の健全な土壌を保証している。その機能的効果に関する限り、生産の分離は生産プロセスの「分離」だけでなく、プロジェクト全体の商業的運営における細かい分業も意味し、多くの場合、生産委員会内に集められます。 . 十数人、場合によっては数十人のメンバーの力で、大企業グループにも負けない競争力を形成します。新たな製作委員会モデルの確立は、Web2.0の資本主義独占体制への逆流ともいえるもので、個人の価値や優位性を維持できるよう、環境を次々とDAO化していきます。
「製作委員会モデルは、より多くの企業がアニメ産業に参加することを可能にし、業界全体の発展を促進します。製作委員会は、日本のアニメ会社の最大の問題である物流チャネルと販売を開発するための十分な資金の不足を解決しました」ディズニーの独占のもとに存在する日本のアニメーション会社は、ビジネス帝国のイメージとは異なる。
製作委員会の分散型構造は、クロスメディア制作に関わる業界全体の力関係を総動員し、商品企画、商業運営、流通ネットワークなどの様々な力を結集し、伝統的な要素も取り入れていることが分かる。単一のアニメーション作品をより広範かつマクロな商品ネットワークの観点から捉えます。つまり、製作委員会によるリソースの統合と事業分担は、作品の制作を中心に展開され、最終的には作品そのもののサービスを効果的に実現するものであり、多様なテーマの作品の撮影・制作に強固な基盤を提供するものであり、同時に、アニメーション制作の全プロセスに参加し、会社自体のビジネス関係を拡大します。
最後に、記事の冒頭で提起した重要な質問に戻りますが、ブランド プロジェクトの当事者は、分散型のコンテキストでブランドとその IP の品質と創造的なプレゼンテーションを確保するためにどのように主張すべきでしょうか?日本アニメーション製作委員会の事例から、私たちは階層的な配信、窓口ベースの運営、集中的なコミュニケーションの大きな利点を発見しました。これらは、中小規模のブランドプロジェクト関係者が足場を築き、場を作るための貴重な鏡となります。 Web3.0の経験で。
投資の多様化によりブランドIPの強固な基盤が形成され、運営窓口により各メンバーの合理的な事業配分が保証され、ブランドの品質と影響力の向上に全力を尽くすことができます。他の分野やトラックでのブランド IP の物語の拡大につながります。
参考文献:
参考文献:
王沈:「アニメーション製作委員会モデルの発展と現状に関する研究」、『河南大学芸術学院紀要』、2014年9月。
ウー・ザンウェイ:「日本アニメーションのビジネスモデルの進化とその参照意義」、『学術交流』、2008年11月。
イン・リャンフー:「日本アニメーション産業の主流投資モデル——作品製作委員会モデルと事例分析」、『現代コミュニケーション』、2012年。
サンウェンエンタテインメント「日本の製作委員会モデルはもう古いのか?」 」、2018年4月12日。