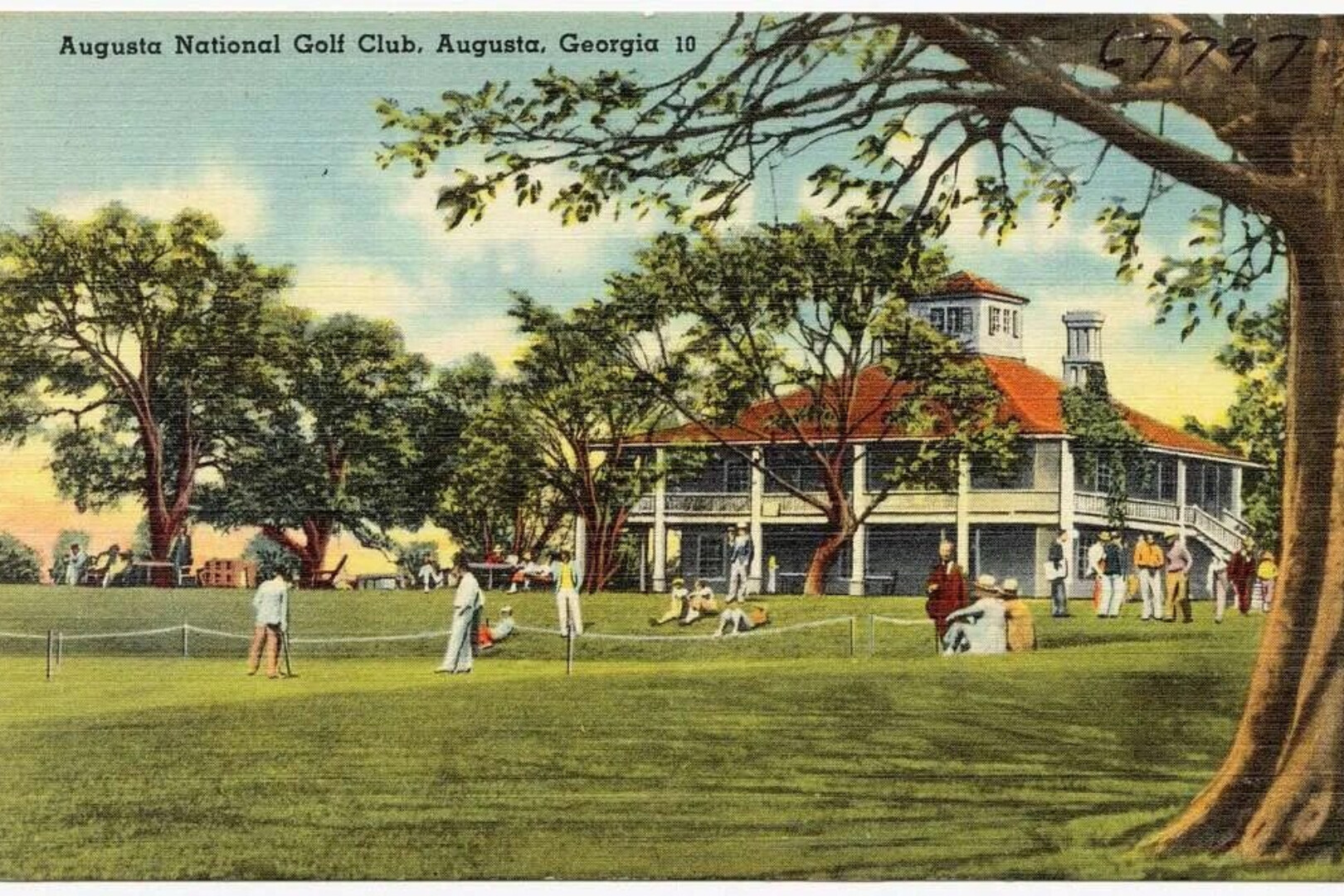オリジナル編集: TechFlow Intern
オリジナル編集: TechFlow Intern
Bakktの委託による調査では、ジェンダーギャップが縮まり、女性投資家が急速に仮想通貨分野に参入していることが示されている。 「女性と仮想通貨」と題された論文では、「仮想通貨の初めての購入者として女性の数が男性を上回っている」と述べられている。
Bakkt は自らを「世界的なデジタル資産規制エコシステム」と称しており、この論文の研究目的は次のとおりです。「暗号通貨における男女格差は十分に文書化されているが、業界がより包括的な方法でどのように前進できるかについてのデータはほとんどありません。この論文は、「仮想通貨を所有している女性と所有していない女性の仮想通貨に対する意識と態度、そしてそれが仮想通貨を所有している男性とどのように異なるか」を測定した。
Bakkt 研究の実際の詳細は次のとおりです。
「この研究は、暗号通貨を所有していないが基本的な知識を持っている女性508人、暗号通貨を所有している女性254人、暗号通貨を所有している男性250人を含む消費者1,012人を対象に調査を実施し、2022年2月に現地調査を実施した。」
もう 1 つの重要な特徴は、この研究で「3 つのカテゴリーのうち、25歳から44歳の人が多い”。
数字を見て、同社が何を発見したかを見てみましょう。
Bakkt のデータは何を示していますか?
これは米国で行われた研究なので、結果を全世界に当てはめることはできないかもしれませんが、興味深い数字です。バックト氏は次のことを発見しました。
「男性は暗号通貨を早くから利用していましたが、現在では女性の方が男性よりも初回購入が多いです。過去 6 か月以内に初めて仮想通貨を購入したのは女性の 38% であったのに対し、男性は 30% でした。 」
「現在仮想通貨を所有していない女性が認識している最大の障壁は、始め方を知らない(52%)、仮想通貨ユーティリティを理解していない(52%)、そして追加投資資金が不足している(49%)ことです。」
「仮想通貨所有者の大多数の男性(69%)と女性(54%)は、今後6か月以内に保有資産を増やす計画があると述べています。」
「ほとんどの女性 (61%) が所有する仮想通貨は 500 ドル未満です。」
暗号保有者 VS コインレス
仮想通貨分野に参入する最も早い方法は直接購入することであることに疑いの余地はなく、それに代わるものはありません。バックト氏の研究のこの部分では、仮想通貨を持たない人々は仮想通貨の世界に迷い込んだように感じる可能性があるため、男性と女性の違いは後回しにされている。
暗号通貨の所有者は、暗号資産を直接経験したことがない人よりも、そのテーマについてよく知っていると感じています。 Coinless の 70% が「自分たちの暗号通貨の知識レベルが低いか非常に低い」と評価しているのに対し、自分の知識を低いか非常に低いと評価している暗号通貨所有者の男性はわずか 13%、女性の暗号通貨所有者は 22% です。
女性のコインレスチョイス暗号通貨に対する見方を表すトップワードは「紛らわしい」「危険」「怖い」。 「一方で、男女問わず仮想通貨所有者」は、次のような共通の流行語をいくつか共有しています。「機会」「成長」「大胆」「革新」。
女性だけのグループでは、「仮想通貨を購入したことのある女性の 82% は、将来も購入する可能性が高いと回答しています。」。
しかし、これらの新規参入者は何を購入しているのでしょうか?バック氏によれば、「調査に参加した仮想通貨所有者は男性も女性も、主な投資先はビットコインとイーサリアムだと主張した。」以下は、インターネット上で最も人気のあるミームコインである DOGE についての言及を含む、より詳細なチャートです。
他の組織
もちろん、このデータを研究している機関は Bakkt だけではなく、最近他の機関でもデータ調査が行われています。おそらくこれらの紙は女性の日用のものでしょう、それはとてもいいことです。最近、BlockFi は同様の研究結果を発表し、次のように要約しました。
BlockFiの新しい調査によると、女性はこれまで以上に暗号通貨に興味を持っており、3人に1人が今年デジタル資産を購入する予定であることがわかった。さらに、これらの女性の 60 パーセントは、今後数か月以内にそうするつもりだと答えています。
「2021年9月に実施された調査と比較して、今回の調査では女性の関心が倍増していることが示されており、その結果、女性の29%が来年の仮想通貨の購入に関心を示しています。」
最後に、Bakkt の最高製品責任者、Nancy Gordon の言葉を引用しましょう。
「最近の仮想通貨の不安定さにもかかわらず、女性が仮想通貨に参入する勢いは続いており、教育を通じて参入障壁を克服できるのは心強いことです。」